突然柔道の世界に飛び込んで、まだ半年もたたないというのに、息子の学校では3年生の仮引退を機に、次の部長を選出する流れになり始めています。
通常であれば、2年生が後を継ぐ…のですが、息子の所属する部活では、2年生がいないため、息子を含む1年生の中から次世代の部を牽引していく代表を選出する運びとなります。
とはいえ、1人の経験者を除いてはみんな初心者であり、実力はほぼ横並び。ならば、柔道経験者の子が部長に任命されて決まりかな?と、私も息子も思っていました。
ところが、顧問の先生の方針はそうでもなかったようで、ひとりひとりにチャンス?を与えてくれました。
中学校柔道部の部長決め

上の娘が中学の時吹奏楽部では、立候補からの3年生を含む部員による投票で部長を決めたため、「人気のある人物」が役職に就きやすい傾向にありました。人気投票が必ずしも悪いわけではありませんが、その人物の本質を知ることなく決まってしまうというデメリットが大きかったです。
【高校吹奏楽部】次世代の幹部・学生指揮の決め方 ~とある学校の場合~
しかし、柔道部では全部員に一通り「部長の仕事」の経験をさせてくれます。
部長になりたい子もそうでない子も、まずは体験するのです。
部長体験と言っても、中学の部活動ですからさほど難しいこともなく、とりあえずはあいさつや号令、部員に対しての積極的な声掛け、先生やコーチへの活動報告くらいなものです。
一通りの部長体験が終わったのち、先生からの指名で部長が決定するそうです。
次期部長に指名されるのはどんな子?

息子が先生に聞いた話では、
- 頑張ってほしいと思う子
- 強さや経験は関係ない
とのことでした。
例え下手でも弱くても、柔道を好きになってまじめに取り組んで、みんなのやる気を引き出してくれる子、部員ともめ事を起こさない子、精神的に強い子がいいかな…ってところでしょうか?
部員数も片手に収まるくらいしかいないため、部長とはいっても、そんなに肩ひじ張る必要もなさそうですし、先生も「経験年数や上手下手」で選ばない方針のようです。
立候補でもないし、押し付け合いでもないため、公平な決め方のように思います。
息子は部長を目指しているのか?
「僕にはとても務まりません」
おそらくわが息子は、万一指名されたとしても面と向かって断りそうです。(本来、拒否することはできないでしょうけど)
学級委員はおろか、班長すらやったことがない(やろうとしたこともない)息子です。人をまとめる役が向いているとは思わないので、彼の判断は間違っていないように思えます。ある意味冷静に、自分の分析ができているのかもしれません。
でも、チャンスがあるならば、一度くらいは「経験として」人をまとめることをやってみることも大事ではないかな?と親心には思ってしまいます。
さいごに
息子たちの世代は、2年後に決定している部活動の地域移行化が始まる前の「学校の部活動として最後となる部員」です。顧問の先生も、最後の活動に向けていろいろ考えてくださっていることに感謝しています。
そして今回部長に選ばれた子は、卒部までの2年間の任期だそうです。
まだ決まるまでには少し時間がかかりますが、任期も長いため、子どもたちが納得し、活動に協力しあえるような決め方であってほしいなと思います。


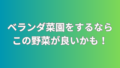
コメント