母子生活支援施設は、外観は普通の集合住宅のようなつくりになっていますが、内装はやや特徴的なつくりとなっています。保育園や学校のようなつくりである建物の中に、教室ではなく居室があって、そこで多くの母子が生活をしています。
今回は、共同生活に近い「母子生活支援施設」の設備と、利用にあたってのルールを書いていきたいと思います。
母子生活支援施設の設備

見た目は普通の集合住宅のようではありますが、その建物内はやや特殊なつくりとなっています。
玄関
入り口に居室ごとの下駄箱が設置されており、各部屋で割り当てられた下駄箱を使うことになっています。そこで外履きを脱いだら、以降は内履きで移動します。保育園や学校と同じ感覚ですね。
職員室(事務室)
入口すぐに、職員が常駐している事務室があります。事務室の前を通らないと居室に向かうことができない造りとなっていますので、必ず職員に顔を見せることになります。だからといって必ず声をかけなければならないというものでもなく、会釈程度で通過しても何ら問題ありません。
入口近辺に事務室がある理由は、入居者以外の侵入を防止するためであり、女性と子どもが暮らしている建物を守るためでもあるのです。
事務所には必ず職員がいて、夜間も宿直の人がいて緊急時には対応をしてくれます。
プレイルーム(学習室)
学童保育をおこなったり、季節のレクリエーションをおこなったり、雨の日に子どもたちが集まったり、地域の人に貸し出して集会が行われたり…いろいろな使われ方をしている部屋です。
貸し出しの本や、乳幼児が遊ぶことのできるおもちゃやゲームが備えられており、子どもたちの交流の場となっています。
面談室
入居者の個人面談が行われる場です。面談の頻度は、人によりますが、2~3か月に1回程度だったように感じます。
一時保護室
緊急に保護された人が生活する場です。職員室の隣に置かれ、簡単に他人が入ってくることができないようになっています。いわゆる女性シェルターに近い部屋です。
保育室
就学前の子どもを預かってもらう部屋です。
基本的には未就学児は、入居してから近隣の保育園への入園手続きをして保育園に通わせる運びとなるのですが、待機児童等などで、近隣の保育園の利用ができない場合、施設内の保育室の利用ができます。
外遊具
ちょっとした広場と遊具も、施設の敷地内に備え付けられていることがあります。こちらも入所者全員での共有となりますので、譲り合って利用します。子どもと共に外にいることで母親同士の交流が生まれることもあります。
母子生活支援施設ので暮らしていくうえでのルールとは?

家庭ごとに居室が与えられているとはいえ、1つの建物で多くの世帯が生活しているため、お互いが気持ちよく生活するためのルールは決められていました。
門限
女性と子どもが暮らす、児童福祉施設ということもあり、夜間は施錠して外部から他人の侵入がないように管理されています。
施設ごと異なるかもしれませんが、私がお世話になったところでは、22時から翌6時までは完全に施錠されていました。
万一仕事などで門限に間に合わない場合は、事前に申請しておくことで職員さんが対応してくれる場合もあります。どうしてもというときには相談しましょう。
掃除当番
共有部分である廊下の掃除を日替わりで行っていました。1,2週間に1回くらいのペースで順番が回ってきます。日中のうちにすることとされていましたが、仕事に行っている人は仕事前か、帰宅後にしている人もいました。
戸締り当番
月1回程度、共有廊下の窓閉めの当番がありました。これは全フロアの廊下を見て回る当番でした。防犯上のこともありますが、夜中に雨が降りこむことを防止する意図もあったかもしれません。
当番の日は、終了したら職員さんへの報告もおこないました。
会合
月1回程度、母親のみが集まってちょっとした話し合いが行われていました。
- 職員さんからの話
- 苦情等の共有
- 以後の行事の案内
- その他連絡事項 など
全員が1か所に集まって、ちょっとした話し合い(連絡事項伝達)が行われます。時間にして1時間弱、町内会の会合と比べればあっさりしたものです。
外出・外泊届
職員さんは、利用者の安全を見守る義務があります。そのために、都度外出・外泊の把握をする必要があります。特に外泊に関しては取り決めが厳しく、書類の提出、担当職員・施設長の許可が必要であり、外泊の理由も厳しく決められています。
- DV被害者が外泊中に加害者と接触する
- 他の異性と外泊する
- そのまま行方をくらます
- 外泊中に警察沙汰を起こす(または巻き込まれる)
などを防ぐことにもつながります。
外出に関してはそれほど厳しくはないものの、長時間の外出(仕事や職業訓練も含む)になる場合は、事前に行先(職場など)の連絡先を届け出ておく必要があります。(仕事に関しては、職を変えない限り初めの1回の申請で良かったです。)
防災訓練の参加と健康診断
防災訓練は年1,2回は消防士さんが来て、行われます。防災訓練はほぼ強制参加となります。
また、年1回母親を対象とした健康診断も行われます。こちらも必ず受けるように指導されます。(職場で健康診断がある人は結果の提出のみで良いです)
さいごに
私は実際に、1年8か月ほど母子生活支援施設で生活をさせてもらいました。今回は、その経験をもとに、生活するうえで必要なルールを中心に書いてみました。
通常の集合住宅で暮らすことを思うと、少しばかりルールが厳しいようにも思いますが、ちょっとした共同生活のようなものですので、ある程度の決まりも仕方がないと割り切るしかありません。
私自身は、このルールにやや面倒くさいと感じることもありましたが、ものすごい負担に感じていたわけでもありませんでしたので、掃除はもちろん、会合もほぼ出席していました。中には、窮屈に感じて短期間で退所してしまった人もいるので、感じ方は人によるといったところです。
母子生活支援施設ってどんなところ?良かったところと不便だったことは?
【母子生活支援施設】実際の入所経験者が感じたメリットデメリット~母子生活支援施設へ入所する前に~
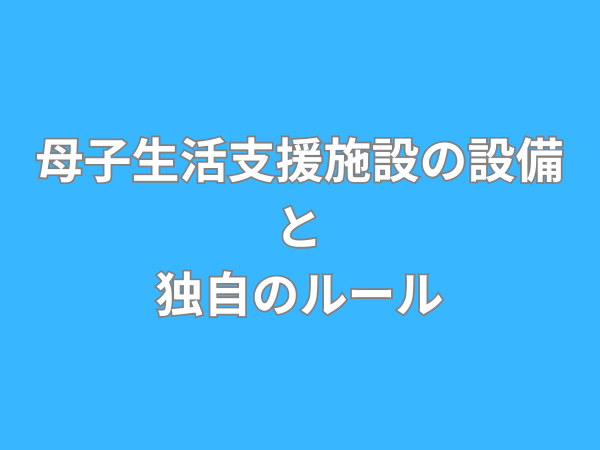

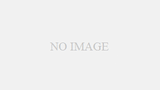
コメント