娘が所属している中学校の吹奏楽部。
次大会の出場枠をかけての地区大会と県大会が行われました。
コロナ拡大による大会の中止も懸念されましたが、今年度は少しだけ形を変えて行うことができました。
2年ぶりの全国吹奏楽コンクールが行われることに

コロナ騒動が始まった昨年度は、コロナ感染拡大を懸念した結果、残念ながら全国吹奏楽コンクールは中止になってしまいました。
娘の学校でも昨年の3年生は「最後の大会」となるはずでしたが、念願叶わず…学校内で吹奏楽部の保護者を対象としたこじんまりとした「引退コンサート」をおこなって引退するという形となってしまったのです。
しかし、今年度は早々から「コンクールに向けた練習」が行われ、子どもも大人もコンクールが中止になる不安を抱えながらも子どもたちは練習、大人たちはサポートを続けていました。
そして、ついに全国吹奏楽コンクールの中の1つ目の予選となる「地区大会」が行われました。
全国吹奏楽コンクールに存在するいくつもの予選

中学校や高校など、吹奏楽をおこなっている団体は数えきれないくらいあり、どの学校も上を目指して日々練習しています。
私自身は中学生の頃は美術部だったので、「大会」や「コンクール」というものにはほぼ縁がありませんでした。(作品を出品することはありましたが…。)
ですので、娘が吹奏楽部に入ったことでコンクールの仕組みについて知ることができたのです。
まずは吹奏楽連盟は大きく分けて
- 北海道支部
- 東北支部
- 東関東支部
- 西関東支部
- 東京支部
- 東海支部
- 北陸支部
- 関西支部
- 中国支部
- 四国支部
- 九州支部
と、11の支部に分かれているようです。
支部の中は各府県(東京・北海道は各1都道で支部)から構成され、さらに都道府県は学校数に応じて複数の地区に分けられています。
例えば、私が暮らしている静岡では、吹奏楽連盟の東海支部に所属し、静岡県内は西部・中部・東部の3つの地区から構成されています。
つまり、静岡の学校から全国吹奏楽コンクールに出場を狙うのであれば、
- 西部・中部・東部で行われる「地区大会」に出場し好成績を収め、「県大会」へ出場する。
- 「県大会」で好成績を収めて「支部(東海)大会」へ出場する。
- 「支部大会」で好成績を収めてようやく「全国吹奏楽コンクール」への出場が可能になる。
という流れになります。前3つの大会は、全国吹奏楽コンクールの予選扱いです。全国までの道のりは実に険しいものなのです。
中学校吹奏楽部の練習日数や練習法

コロナ・顧問の先生の働き方改革・保護者からの部活動に対する要望…など様々な要因があって2~3年前と比べても練習時間が少なくなっていることは間違いないようです。
平日も週に2日は「部活動をおこなってはいけない日」と決められており、土日も基本的にはどちらかのみの活動とすることが決められています。(大会前は特例もありますが)2年前までは「朝練」もあったのですが、娘が入学した年からはまだ1度も行ってはいません。
昨年にはコロナ禍での学校休業もあり、例年と比べると明らかに練習量が少ないのですが、そんな悪条件にも負けずに娘は部活動を楽しんでいます。
娘は部活動に「行きたい」ということはあっても、「休みたい」とは言ったことはありません。
専門講師による練習
吹奏楽部には吹奏楽経験者である顧問の先生もいますが、顧問の先生も専門外の楽器というものがあります。(というより、1~2の楽器しか詳しくないことの方が多いですね。)
顧問の先生の専門外の楽器を使う子に対しては、外部から講師を招きます。
各パートごとの練習となりますが、1~2か月に1回くらいの頻度で練習を行っています。
また、大会等が近づいてくると全体の様子を指導してくれる講師を招いたりもします。
合同練習
感染症対策をしっかりしたうえで、他校との合同練習を行うこともあります。
娘の学校でも「吹奏楽に力を入れている高校」との合同練習に参加させてもらっています。高校生から直接指導してもらうことで、自分の演奏を客観的に見てもらえるというメリットもあります。
高校生のデモ演奏も聞かせてもらえたりとなかなか充実した合同練習を行っているようです。
ホールを貸し切っての練習
普段の教室練習とは変わって、広い場所での音出しは音の響きの違いを始め、自分がどのくらいの音量で演奏するべきかということを考えることのできる練習です。
コンクールの会場は、学校の教室のように狭い場所ではありません。それなりの広さがあるホールですので、事前のホール練習はかなり重要であることが理解できました。
各イベントへの参加
コロナ禍である現在はまだ難しい状況にありますが、コロナ前は様々なイベントでの演奏も行ってきたそうです。
「学校以外での演奏」を行うことで、吹奏楽部員としての経験値を積むことができるそうです。
静岡県吹奏楽コンクール地区大会

まだまだコロナ感染者が日に日に増える中、吹奏楽コンクールの地区大会が行われました。
例年との変更点
コロナ対策として地区大会も例年との変更点がありました。
- 観客は生徒の関係者のみ(マスクは必須)
- 各校出場時間に合わせての来場
- 出番が終わり、写真撮影が済んだら速やかに帰宅
例年は、一般のお客さんも入場することができたし、出場者は閉会式まで残って表彰式に出たりもしていました。しかし、人が集まり過ぎることを懸念してか、滞在時間がなるべく短時間になるように配慮された形となりました。
打楽器はマスク着用?
出場校の打楽器は学校によってまちまちでしたが、「マスクを着用」して参加している学校もありました。しかしマスクをしていない学校もありましたので、「決まり事」ではなかったようです。
コンクール結果の伝え方
上にも書きました通り、例年は表彰式まで出場者が滞在しているため、閉会式時には結果がわかります。しかし、今年度は「演奏が終わったら帰宅」ですので、子どもたちが直接結果を知ることはできません。
今回は、顧問の先生が一人最後まで残って結果を聞いてくるということになっていました。県大会に進むことが決まった学校には、賞状とトロフィーが配られ、顧問の先生はその場で県大会の順番のくじ引きを行い、当日の打ち合わせを行ってから帰ってくるとのことでした。
その後は、保護者会の役員を通して一斉に保護者会のLINEで各家庭に結果が伝えられます。
娘の中学校 地区大会の結果
近年、娘の通う中学校では地区大会銀賞が最高位であり、長い歴史の中でも県大会に行くことはほとんどないような学校でした。
しかしながら、今年度は見事に地区大会を突破し、県大会への切符を手にすることができました。
実は、今回参加した生徒全員が初めての大きな大会となりました。直前まで「銅賞演奏」と言われ続けていた集団でしたが、本番ではしっかりとした恥ずかしくない演奏ができていたと思います。
この大会の結果は、保護者会のLINEで知ることになったのですが、結果を聞くなり娘は感極まって大泣きしてしまいました。
うんうん、頑張ったもんね。だけどね、まだまだ先があるからここで満足してはいけないよ…。
地区大会終了後
演奏終了後に現地で解散した際、楽器運びの手伝いに来てくれた1年生に対して2,3年生が「ありがとうね。」とお礼を言っていたことが印象深かったです。
演奏したのは主に2,3年生でしたが、裏方で1年生が手伝ってくれたおかげで良い演奏ができたことを感謝する気持ちが持てている先輩たちの姿が素敵でした。
帰宅後娘にそのことを伝えると、「え?そんなこと当たり前じゃないの?」と言われてしまいました💦本心からそう思える子どもたち、えらいぞ!!
私たちがこのくらいの時は「先輩」がやたら威張っていて1年生は裏方参加が当たり前くらいに思っている人が多かった世代なので(笑)今の子の大人な対応に親としてうれしくもあり、大人としてはちょっと恥ずかしい気持ちになってしまいました💦
「私たちの夏はまだ終わらないし、終わらせない!!」
と息巻いている吹奏楽部員。次の県大会もがんばれ!!
全国吹奏楽コンクール静岡県大会

地区大会からおよそ1週間、何事もなければ県大会の舞台に立つことができたのかもしれません。しかし今はコロナ禍、大会目前で静岡県下は「まん延防止等重点措置」の対象となることが決まってしまったのです。
実際には大会当日はまだ対象となる期間ではありませんでしたが、静岡吹奏楽連盟の判断により、県大会は行わず、地区大会の音源での審査となることが決定されてしまったのです。
結果は惜しくも銀賞。
しかし、ここ近年成績が伸び悩んでいた娘の学校の吹奏楽部ではかなりの快挙でありまました。結果としては、記録に残っている中では歴代の中でも最優秀でした。
審査方法は他になかったのか?
地区大会終了から約1週間、子どもたちは毎日練習を行っていたのですが、その成果を見せる場もなく、「地区大会での音源」で審査するという決定を残念に思いました。
今はYouTubeを活用した大会も行われています。実際に今回、高校生の部ではYouTubeでの生配信をおこなっていたのです。
各学校から生配信という形でもできなかったのかな?
また、各学校でCD録音をしてその音源で審査…とかも不可能ではなかったはずです。
地区大会の音源審査の不公平さはないのか?
まずは、音源が撮られた場所が地域ごとで異なることです。
地区大会そのものはそれなりのホールで行われるのですが、ホールによっても作りが異なるため、音の響きが全く異なります。
実際に、娘は地区大会の会場を含む2か所のホールで事前に練習したのですが、地区大会でも使用されたホールでは「まったくと言ってよいほど音が響かない」とのことでした。そしてもう1か所のホールでは「ものすごくうまく聞こえるくらい響くんだよ~。」と言っていたのです。
今回、中部地区の大会に使われていたホールは「全国で最も響かないホール」とも呼ばれている会場でした。中部地区から県大会に出場した子はみんな「最も響かない悪条件のホール」での音源で審査されることになってしまったのです。(結果みんな仲良く銀賞でした💦)
せめて同じような条件の場所、「学校の体育館」などと統一してくれればもう少し公平になったのではないかと感じます。
県大会の結果を聞いた子どもたちの様子
県大会の発表は、吹奏楽連盟のホームページから各自自宅で確認することになりました。今は、子どもも大人も連絡先はLINEでつながっていますので、結果を知った子から順に連絡が入ってきます。
- よく頑張った!!
- 県大会の場で演奏できなかったけどやり切った!
- 部活引退したくないよ~
- 吹奏楽部最高!!このメンバー最高!
- 部活のグループラインから抜けたくないな…
- 個々にLINEの友達になろうぜ!(グループから抜ける前に)
など、子どもたちの中では意外と結果うんぬんという感じではありませんでした。
娘も言っていましたが、「音源審査」に変わったことにより、「うれしさ」も「悲しさ」も「残念さ」もないそうです。 ただ淡々と終了した感じ…だったそうです。
他の子も同様で、「結果」に対してより、「同じ吹奏楽部員の先輩(3年生)」との交流が断たれてしまうことへの寂しさを感じている子が多いように感じました。
吹奏楽部では珍しく(?)部員全員の中が良い学校ですので、こんなやり取りになったのでしょうね。
さいごに
吹奏楽の大会で「駒を一つ進める」という目標を達成した子どもたち。
県大会では予期しない審査からの結果となってしまいましたが、これもコロナ禍ならではのもの…ということで大人になってからの「思い出話」の一つになるのではないかなと思っています。
それにはもちろん「コロナ撲滅」をしなくてはならないのですが…。
いつか「良い思い出話」となることを期待しながら来年度の大会まで応援したいと思います。
ちなみにこの後は3年生が引退となりますので、世代交代をします。娘たち2年生の中から次世代を率いていく子を選んでいくという大仕事も控えています。こちらも温かく見守っていきたいなと思っています。
【高校吹奏楽部】次世代の幹部・学生指揮の決め方 ~とある学校の場合~
高校「吹奏楽部」へ入部 中学と高校での活動に違いはあるのか?
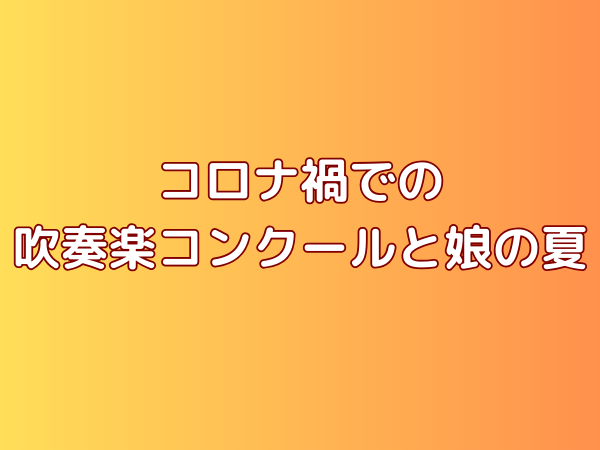
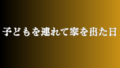
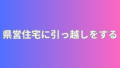
コメント