娘の通う学校の吹奏楽部では、3年生の退陣に伴い、部の新たな運営メンバーを選出して活動を始めて、しばらくが経ちました。
それまで、「サブインスペクター」として部内の「行動予定計画係」として正インスペクターと共に活動していた娘は、先生からの指名で「学生指揮長」(長というのはサブもいるので)として、部内の音楽的な取りまとめをする立場となりました。
【高校吹奏楽】インスペクターって何?
【高校吹奏楽部】次世代の幹部・学生指揮の決め方 ~とある学校の場合~
娘は、それまでの「行動予定計画係」の仕事とは種類の異なる「学生指揮」という立場に少し戸惑いつつも、この数か月間何とか仕事をしてきたそうです。
今回は、娘の学校での「学生指揮」の役割を書いていきたいと思います。
学生指揮の選出方法

先代までの学生指揮に関しては、3年生からの指名で決められていました。
生徒同士で決めていましたので、選ぶ側の生徒の力量で、次世代のバンドをまとめる人材のまともの選出ができるか否かが決まってしまうという、少しリスキーな選出方法でもありました。
いくら吹奏楽部の先輩とはいえ、
- 高校から始めたばかりの先輩(後輩のほうが吹奏楽歴が長い)
- 譜読みが苦手な先輩(正確に楽譜が読めない)
- ただただ好きな楽器を弾いて(吹いて)みたかったがために入部した先輩(このタイプは目的を達成したらそれで満足してしまう傾向にある)
など、「音楽にたけている人」ばかりではないという現実もあります。
その先輩たちからの指名では、「正しい選出」ができるかどうかは少し怪しいです。
ということで、今回からは音楽講師の先生(以下先生)からの指名制度に変更されました。
幹部決めの優先順位
学生指揮の選出方法変更に伴い、部内幹部の選出方法も変わりました。
- まずは、部員の中から「学生指揮長」「サブ学生指揮」各1名ずつを先生が指名。
- 残りの部員の中から、幹部候補4名を3年生が選出。
- 幹部候補で選ばれた4人の部員で話し合いをして役職を決める。
学生指揮が2人いるのは、木管と金管から各1名ずつ選出するためであり、基本的には学生指揮長が取りまとめることとされています。
学生指揮の仕事

先代までの学生指揮の仕事は、
- 基礎合奏の計画・実行、とりまとめ
- 先生不在時のイベント指揮(コンクール以外)
くらいのものでした。
しかし娘に関しては、上記に加えて
- ネット上の曲など、耳コピだけで2~4小節くらいの楽譜を作る
- 先生が指定した箇所、数小節分の編曲(全パート)
など、楽譜をいじる作業まで任されています。
学生指揮を始めて感じたこと

まだ学生指揮になってから日が浅い娘ですが、彼女なりに感じることもいくつかあったようなので、良いこと悪いこと含めて書き出してみたいと思います。
学生指揮になって良かったこと
- 先生の指名で選ばれたこと
- 音楽系の部活にしかない役職
- 先生から直接音楽的な知識を教わることができる
- 基礎合奏など、みんなの前に立つ経験
先生の指名で選ばれた
選出の際、「適材適所であってほしいから僕自ら選びたい」と宣言していた先生から、直接指名されて学生指揮長として活動をすることになった娘。
音楽的なセンスを認められてこその選出だったことに、モチベーションが上がり、自らの自信にもつながったことが良かったと思っています。
音楽系の部活特有の役職
学生指揮は、他の文化部や運動部にはない専門的な役職であり、部長や副部長より「専門性が必要」な立場であるため、やりがいを感じるのではないかと思います。
先生から直接、音楽的な知識を得られる
卒業後の進路を「音楽系の仕事」と決めている娘に関しては大きなメリットです。
部内での練習方法、基礎合奏の在り方、パートごとの強化方法など、音楽的なことは唯一先生と対等に話すことのできる役職なので、直接アドバイスをもらうこともできます。音大を出ている先生と話すことができるのも大きなメリットです。
また、楽譜の編曲や、作成などにも関わらせてもらっているので、その経験も今後生かしていけるのではないかと思っています。
みんなの前に立つ経験
娘は本来、人の前に立つことを得意とする性格ではありません。でも目立ちたがりではありますので、ソロ演奏などはそつなくこなしています。
なぜ人前に立つことが苦手なのか?というのは、「人前で話すことが苦手」であるかららしいのです。
学生指揮となると、基礎合奏時に「みんなの前で意見」を言わなければならず、それが娘にとっては辛いとのこと。しかし、苦手なことでもやらざるを得ない状況になればなんとかなるようで、「意見を言うこと」も次第に慣れてきている様子。
親としては、社会に出るまでに苦手克服という意味で良かったことかなと感じました。
学生指揮になって感じたちょっと悪いこと
- 部長が出しゃばりすぎ
- バンドの弱みが見えた
部長が出しゃばりすぎ
学生あるあるかもしれませんが、学生指揮である娘を差し置いて、部長の子が基礎合奏に口出しをしてきてしまうらしい。決まって「私が部長だから」と言ってくるとか…。
それによって、娘がやりたい練習が思うようにできていないとのこと。
部員を統括してまとめるのは部長ではありますが、専門性の高い音楽的なことは娘が任されていますので、「やりづらい」と感じているのであれば、何かしら対策をとらないといけないのでは?と思っています。
娘は行事・コンクールがいったん落ち着いた時期を見計らって、先生と部長と話をする時間を設けたいとは言っていますが、いつになることやら…
バンドの弱みが見える
前に立って音を聞いていると、バンド内の弱みがはっきりとわかるそうです。(これは良いことでもあります。)
もちろん、それを直すことが娘に求められている仕事ではありますが、音楽は抽象的なことも多く、言いたいことが伝わらない場合もあるのです。
また、一度注意したことでもすぐに忘れてしまう部員もいて、やりづらさを感じる…と言っていました。
娘は、「良い人を引き合いに出して教えていく」という方法をとっているとのことでしたが、これからもうまくいくか心配な点でもあります。
学生指揮としてこれからどうしていきたいか考える
娘の高校の部活の先生は、いろんな高校や中学にも指導に言っているため、不在なことも多いです。その穴を埋めるための学生指揮ですが、先にも書きましたように、「思うように活動ができていない」のが現実です。
娘は、
- 基礎合奏のメニューなどは、状況に合わせて自分が良いと思う内容でおこないたい(部長には、口出ししないで見守っていてほしい)
- セクション練、パート練を充実させたい(まずは少人数で合わせていきたい)
- あまり上手でないパートの練習に付き合い、底上げを図りたい(パートごとの進捗具合の把握もかねて)
- まずはパート内での良い雰囲気づくりをしっかりできるようにしたい(音は奏者の気持ちが出やすいことから)
と考えています。
しかしながら、いまだに先生とも部長とも腹を割った話ができていないようです。
さいごに
学生指揮の抜擢された娘は、「頑張ろう」という気持ちと、部長が出しゃばってくることによっての「私の存在意義ってなんだろう?」のはざまにいるように感じます。
本当は初めに先生から「音楽関係のことは一任する」とはっきり言ってもらえていたら、また状況は違っていたかもしれませんが、今のところは実質部長が取り仕切ってしまっている状況であると言っていました。
先生も、「適材適所」といって決めいたことであるのなら、そこのところの指導はしっかりとしていただきたいのですが…。
これも高校吹奏楽あるあるなんでしょうかね?
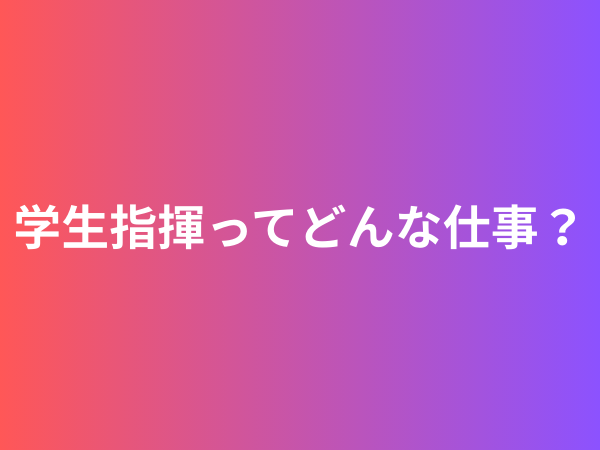
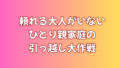
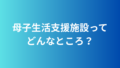
コメント