我が家の長女は、小学4年生のときにはすでに「中学校に行ったら吹奏楽部に入る!」と宣言していました。
そして2020年度、念願の中学生になったのですが、コロナ騒動で幕を開けた新学期。
中学校では、本来ならば5月中に行われる、新1年生を対象とした部活動の入部希望の調査は省略されました。6月に入り、親も子も「部活動はいつ決まるのかな?」と思って待つ中つい先日、部活動の見学からおこなうことができました。
令和時代の中学校の部活動は強制参加ではない?

私が中学生の頃(ざっと四半世紀前(;^_^A)は、部活動は全生徒加入するものでした。(学校や地域によって違いがありますかね?)
ところが、今どきの中学校では「部活動をやりたい子だけ入部」という方針になっています。
これは、「中学校の先生の働き方改革」と「生徒の校外での習い事やクラブ活動」に配慮されたものとなっているようです。
中学校の部活動は週にどのくらい活動するのか?
地域差はあると思いますが、私の居住地域では基本は、平日夕方週3回+土日のいずれか(昼またぎ)試合や大会などを控えている部は、これにプラスして練習日が増えることもあります。
帰宅部の選択はありなのか?
帰宅部…要するに部に所属もしないし、郊外での活動も行っていない子のことを指します。
校外で活動を行っていない子に関しては、いまだ入部を勧めてはいるようですが、もちろん強制ではありませんので、「帰宅部」の子ももちろん存在します。
部活動はやるべきか?
この先高校に進学することを考えると、「部活動」はやっておくに越したことはありません。校内での活動は高校受験には良いアピールポイントとなります。
(居住地域では、段階的に部活動の廃止が決定しており、2027年度には地域のクラブ活動という形に完全移行するとのことです)
もちろん校外での活動も、成績を残すことができれば加味してもらえるかもしれませんが、成績表には学校生活について教員が記録するものとなりますので、郊外での活動よりも校内での部活動の方が評価点は大きくなりがちです。
ですので、「帰宅部OK」の学校であっても、進学を考えるのであれば、何かしらの部活動はしておいても損はない活動になります。
部活動の見学(わが子の学校の場合)

ひとり3つまで気になる部活動の見学に行くことができます。3回とも異なった部活動を見るもよし、3回とも同じ部活動をじっくり見るもよし。
我が家の娘は、始めに書いたように「吹奏楽部」一本に決めていましたので、3回あった見学はすべて吹奏楽の見学に費やしました。
ピアノは習っているものの、吹奏楽部でどんな楽器をやりたいかはまだ決まっておらず、漠然と「フルートかクラリネットみたいな木管楽器がやりたい」と言っていました。音楽関係は唯一リコーダーが壊滅的にヘタな娘ですので、正直心配です。
実際に3回見に行った感想を聞くと、「先輩にね、『何の楽器がやりたいの?』って聞かれた~。」と、のんきな言葉が返ってきました。
体験入部 1週目(1~3日)

中学校では、平日に2週間かけて体験入部もします。とはいっても、平日の活動日自体は週3回ですので、全6回ほどの体験入部となります。
ここでも、気になる部活動が複数ある場合は、日に分けて体験することができますので、6回の体験入部期間に複数の部活動の体験をおこなって、じっくり考えることもできます。
吹奏楽の体験入部期間では、日に分けて一通りの楽器の音出しをさせてもらえます。
1日目 トランペット チューバなどの金管楽器
娘にとって金管楽器は、眼中にありませんでした。
両楽器共に人生初体験でしたが、筋が良いのか運が良いのか、いきなり音を出すことができたようです。金管楽器は、息の入れ方で音の高低を出すため、演奏するとなるとかなりの練習が必要になりそうです。
そしてこの日帰宅した娘は、「私、トランペットをやってもいいかも…。」と、金管楽器にも少し興味を持ったようでした。
2日目 打楽器
マリンバ、ビブラフォン、大太鼓、シンバル、ドラ(笑)、ティンパニー、ドラムセットがあります。一通り叩いたようですが、娘はマリンバとビブラフォンの鍵盤楽器にかなりの時間を費やしたそうです💦
ピアノを習っている子ですので、音階はすぐにわかるため、曲として演奏できるものが面白かったようです。
しかし、打楽器に関しては触っても興味が沸く様子はなく、残念ながら特に「やってみたい」とも言ってはいませんでした。
3日目 いきなりの自由(笑)
金管楽器、打楽器ときたら3日目は『木管楽器かな』と思うところでしたが、なんと急に自由となりました。
本入部のための日数調整のため致し方なく…といったところでしょうか???
ともかく、3日目は突然訪れた自由行動であったため、娘は念願の木管楽器(フルート、クラリネット)を回ったとのこと。
フルート
初体験でいきなり音が出て、顧問や先輩を驚かせたようです。
顧問の先生には「筋がいいね…」と言われたようで、嬉しそうにしていました。
あっさり音が出せたため、ドレミファソの5音の指使いも教わり、初日の数分でこの5音もなんとなく吹けるようになったようです。
けれど、フルートを希望している子は多く、今のところ倍率が一番高い楽器のようです。フルートパートでは、練習するためのストローをもらって帰ってきました。
クラリネット
この日、体験入部に来ていた1年生全員にクラリネットのリードを一つずつ配ってくれました。
リードとは一見アイスのスプーンみたいにも見えますが、マウスピースに装着して振動させることで音を出すので、クラリネットには必要なパーツとなります。
フルートに続いて、こちらでもあっさり音を出すことができ、周りをざわつかせていたようです。「何度も『本当に始めて吹くの??』と先輩に確認された。」と言っていました。
第1週目の体験入部 が終了して
体験入部前、漠然と「フルートかクラリネットがやりたい」と言っていた娘。1週目の体験入部が終わって、再びどんな楽器をやりたいかと聞くと、
- 第1希望 フルート
- 第2希望 クラリネット
- 第3希望 トランペット
と、フルート希望である気持ちが変わることはなかったようです。
体験入部2週目(4~6日)

娘は「入部するなら絶対吹奏楽部」と決めていたため、6日ある体験入部期間はすべて吹奏楽部で過ごしました。
2週目となる4日目以降は、本入部の希望調査と、 希望楽器の調査が主だった内容となりました。
4日目 第一希望楽器を体験させてもらう
実質体験入部4日目となります。この日は、第1希望の楽器のところでの体験となりました。
娘は相変わらずフルートが希望のようで、この日もフルートの先輩について練習させてもらっていました。ところが、やはりフルートは人気楽器のようで、多くの1年生(女子)が集まったそうです。
息の入れ方で音の高さが変わるフルートは音出しも難しく、もちろん1年生は初心者ですのでみんなてこずっていたのです。その中でも娘は「低音がきれいに出ているね」と褒めてもらえたそうです。
5日目 サックスを体験
結果的にドハマりすることになる楽器ですが、5日目にして体験入部の時には一度も名前が上がらなかったサックスを吹かせてもらいました。この日はアルトサックス用のリードがひとり1枚支給されました。
元々音出しのしやすい楽器と言われていることもあって、娘はサックスもあっという間に音を出すことができたようですが、「肺活量が必要な楽器かも…」と感じたようです。
体験入部前は、サックスに全く興味がないようでしたが、実際に触ってみて興味を持ったらしく、体験後には『やってみたい楽器の一つ』になりました。
この日は、先輩の名前と顔もだいぶ知ることができたようで、先輩からもだいぶかわいがってもらっているようで安心しました。先輩との対人関係も良好のようです。
6日目 体験入部最終日
体験入部の最後は、1年生が二人一組になって順番にいろいろな楽器のところに見学&体験に行くことになりました。各パートの先輩が1年生に対して丁寧に教えてくれたそうです。
ただ、この日はすべての楽器をまわることができず、第1希望のフルートも常に人が多く、体験することができなかったと言っていました。
そして、体験入部最終日となるこの日は、『入部届』も配られました。
- クラス
- 名前
- 住所
- 電話番号
- 保護者の名前と印鑑
を記入するようになっており、「入部希望の人は週明けに持ってきてください」と伝えられ解散となりました。
正式に吹奏楽部への入部届を出す

今どきの中学校の部活動は、『親の許可』が必要になります。
私たちの時代(約四半世紀前ほど)は、部活動は『強制入部』であり、学校生活の一部という扱いでした。当時は、子どもから希望を取って調整して入部という流れでした。
それが今では、きちんと保護者印まで押した入部届を提出しないと入部ができないシステムのようなのです。これには少し驚いてしまいました。
部活動本入部

顧問の手元に入部届が届いたら、晴れて部員として活動をすることができます。娘にとっては、念願の「吹奏楽部員」となったわけです。
入部初日
初日の吹奏楽部の活動は、2週間体験入部していて今さらながらの自己紹介と、ちょっとした腹筋や背筋などを鍛えるための体操をしたとのこと。
一応希望楽器も全員の前で発表したのですが、木管楽器(フルート、クラリネット)をやりたがる子が多かったため、娘は楽器決めのオーディションに向けて頑張ろうと決めたようでした。
入部2日目~3日目
2日間にかけて、すべての楽器を体験してみて適性を見てもらうとのこと。適性を見るのは主にその楽器パートの先輩です。
いくつかの項目があり、一人ひとりの1年生に対して先輩たちが顧問から託されたチェックシートの項目にチェックしていくのだといいます。項目は、
- 高音がきれいに出るのか
- 低音がきれいに出るのか
- 肺活量
- 唇や歯の形(楽器に適した形であると、演奏がしやすいということ)
- 音を意識して変えることができるか
などです。
娘は、どの楽器でも『肺活量がある』と書かれていたそうです。へー、そうなんだ~。親である私も知らなかった新発見でした。
この2日間の適正結果を踏まえて、顧問の先生と3年生の先輩が相談しながら楽器を決定していくのだそうです。
この日は、最終的な希望楽器の調査も行い、第1候補~第5,6までの希望を書いてきたと言っていました。
体験入部時の娘の希望楽器は、
- フルート
- クラリネット
- トランペット
- フルート(変わらず)
- サックス(初)
- クラリネット
- トランペット
- 打楽器(初耳でした 笑)
入部4日目 楽器決めオーディション第1審査
顧問の先生だって本当であれば、生徒が「やってみたい」と思う楽器を吹かせてあげたいと思っていることでしょう。
しかしながら、全員で一つの曲を演奏する吹奏楽においては、バンド編成に偏り(メロディー・ハーモニー・ベースなどのバランス崩れ)が出てしまうことは避けなければならないため、また学年での偏りも極力ないように編成させたいこともあり、新入生の担当楽器は適正も見ながら、慎重に決めていきます。
フルート第1次審査
第1希望の楽器を先生と先輩の前で吹きます。その後、先生と先輩が話し合って第1審査での合格者を決めます。
希望者が多い楽器に関しては、この段階で半数に絞り込まれます。ちなみに、娘が希望する「フルート」は、一番人気の楽器であったため、2人の募集枠に対して8人が希望していました。(倍率4倍です)
この日の第1次審査で、フルートの希望者から半数の4人に絞り、翌日にもう一度楽器を吹かせて最終審査を行うことが決まりました。
「低音がきれいに増えている」と評価されていた娘も、フルートの第1次審査を無事通過することができました。
入部5日目 いよいよ担当楽器が決まる
フルート最終審査
各楽器のパートごとに、最終審査が行われ始めたこの日、娘もフルートの最終審査を行うことになりました。
最終審査に残った4人で音出しのテストを受けました。出す音は『ファ』と『ラ』の2つ。どうやらこの2つの音が基本となる音のようなのです。
最終選考に残った4人で順に吹き、結果を待つ形となりました。
結果は、1人は突出して上手だった子が決まり、あともう一人を選ぶところで顧問の先生もかなり迷ったとのこと。結局、フルートを吹く口の形に適した子が選ばれる形となり、娘は残念ながら落選してしまいました。
フルートは、口から頭部管の小さな穴に細く息を入れて音を出す楽器のため、唇が厚い人のほうが音が出しやすい傾向にあるのです。
唇が薄かったり、受け口気味の人は、楽器との相性はあまり良くないとのことでした。
これは楽器の特性上、息を斜め下に吹き入れるためという理由があるからなのです。
飛び入りでサックスの最終審査に参加
フルートの最終審査が終わるころには、すでにいくつかの楽器は担当者が決定していたため、選択肢があまりない中で、まだ最終審査が行われていなかった第2希望楽器のサックスの最終審査に飛び入りという形で参加することを決めたのだとか。
ただし、顧問の先生から第2希望以降で受ける子へは、「第2希望以下の子もほかの楽器の最終審査を受けることができるけれど、第1希望の子から優先に選んでいく」と、こう告げられたそうです。
この段階で、第1希望の楽器になれずに第2希望楽器として審査を受けに来ていた娘は、仕方がないこととはいえ、少し不利な状況になってしまったのです。
この時娘は、「サックスがダメだったら、打楽器(人気のなさそうな)にしようかな」とまで思ったと言っていました。
ところが結果は、第1希望で最終試験に来ていた子2人と、娘の計3人でサックスのパートが決まったのでした。第1希望で受けに来ていた子も定員以上にいたのですが、娘とサックスの相性が良かったのか、まさかの1位通過だったという結果でした。
様々な音域のあるサックス特有の担当決め

サックスパート内では、アルトサックスとテナーサックス、バリトンサックスの3種の担当分けをしなくてはなりません。それぞれが担当音域の異なるため、
- アルトは主にメロディー
- テナーは裏メロやハーモニー
- バリトンはベース
と、それぞれの役割も異なります。
娘の学校では例年、各学年に2人ずつサックスを担当しており、各音域でも学年で一人ずつになるように配置されています。つまり同学年で同じ音域担当にならないように配慮されています。3年生が抜けてしまっても、残った部員できちんと補えるように考えられています。
ところが、今年度は1年生が他学年より大所帯ということもあってか、サックスは2人定員のところ、急遽3人になったのです。(ほかの楽器も定員の増員をしていました)
単純に3人ならば各一人ずつで担当分けしちゃえばよいように思いますが、他学年との兼ね合いもあり、今年度に関しては3年生が抜けた穴を埋めるためにはアルト2人とテナー1人は必ず決める必要がありました。
(バリトンは2年生が担当していたので、次年度募集となりました。)
アンサンブルコンテストを見据えてサックスの編成を考える
毎年冬に行われるアンサンブルコンテストに出場することを見据えて、各音域に人必ず1人ずつは配置できるように考えます。(アルト1st・2nd、テナー、バリトン)
入部したての娘にとっては、まだ少し先の話にはなるのですが、顧問の意向(楽譜の兼ね合いかな?)で、「アンサンブルコンテストはサックスは4重奏で」とのことでしたので、1,2年生の合計が5人となってしまうこの年は、1人出ることができなくなってしまいます。
入部から2週間以上が経過してもまだ決まらないサックスの担当音域決め
サックスの音域決めは、入部から2週間以上が経過してもまだ決まりませんでした。実はこの間に、部の保護者会も行われ、各種注文用紙も私の手元に届きました。
なかなか娘たちの担当音域が決まらないために、困ったことにもなりました。
注文用紙はあるがマウスピースが買えない
娘の学校では、どの楽器もマウスピースは個人持ちでした。
しかし困ったことに、注文用紙は手元にあれど、娘の担当する音域が決まっていない以上、同じサックスといえど、それぞれの大きさが異なるマウスピースの注文すらできない状態でした。
時はすでに7月17日であり、本来であれば夏の「全国吹奏楽コンクール」の地区大会間際の時期です。2020年は大会が中止になってしまったので、結果的には活動に大きな影響はありませんでしたが、なかなか決まらないこともあり、購入する立場である私もモヤモヤしながら待つだけでした。
その間にも、用品の締切日だけが刻一刻と迫っていました…。
娘も練習に集中しきれない?
アルトサックスとテナーサックスでは、持ち方も違いますし、息の入れ方も違います。何年もサックスを吹いている人であれば、サックスの大きさが違ったところで難なく吹いてしまうところですが、つい先日初めて触った程度の超初心者にとっては、マウスピースの大きさが違うだけでも、が大きく異なります。
現段階では、学校の備品のマウスピースを使って、両方の練習をしているそうですが、早いところ決めてもらわないとしっかっりとした練習に移行することができず、いつまでも宙ぶらりんな状態になってしまいます。
子どものためにも、早いところパートを決めてあげてほしかったです。
アルトサックスであれば楽器の購入も検討しようかと思っていた
学校で貸し出してくれるサックスは「老朽化」がひどく、顧問の先生からは「絶対ではないけれど、楽器の購入を推奨している」と言われていました。
購入といっても、1万や2万では買える品物ではありません。
ですが、中古のものでしたら何とか買ってあげることもできるのではないかと思っていまして、遅くとも7月の連休で楽器店巡りをしたいと思っていたので、早いところアルトサックスなのかテナーサックスなのかを決めていただきたかったです。
長い期間を経て担当音域決定
サックスに決まってから、半月以上が経過してようやくテナーサックスを担当することに決定した娘。
1年生3人のうち2人は「アルトサックスがやりたい!」と言っていたことから、娘は「じゃあ私がテナーやるね」とあっさり決めてきたようでした。
サックスと言えば、なんとなく「花形はアルト」というイメージだった私は、娘があっさりとテナーを引き受けたことに少し驚いたのですが、娘に理由を聞くと、
- テナーサックスの音が渋くてかっこいい(確かに!)
- メロディーも裏メロもベースもあって何でもできるから楽しいそう
- アンサンブルコンテストに出たいから(アルトだとオーディションになるから)
とのことでした。娘なりに自分の利益をちゃんと考えていたんですね(笑)
さいごに
小学校の時から「吹奏楽部に入る」と宣言していた娘は、結果的に高校でも吹奏楽部に入部し、先生の指名で「学生指揮」を務めるまでになり、少しですが編曲も携わるくらいになりました。
テナーサックスから始めたサックスですが、この翌年顧問の先生からの指名で、アルトサックスを担当することになり、その後はずっとアルトサックスを吹き続けています。
【中学吹奏楽】娘が突然テナーサックスからアルトサックスへ転向 顧問からの突然の宣告
吹奏楽中学生女子についにアルトサックスを買い与えることなりました【ひとり親の決意】

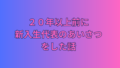
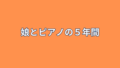
コメント